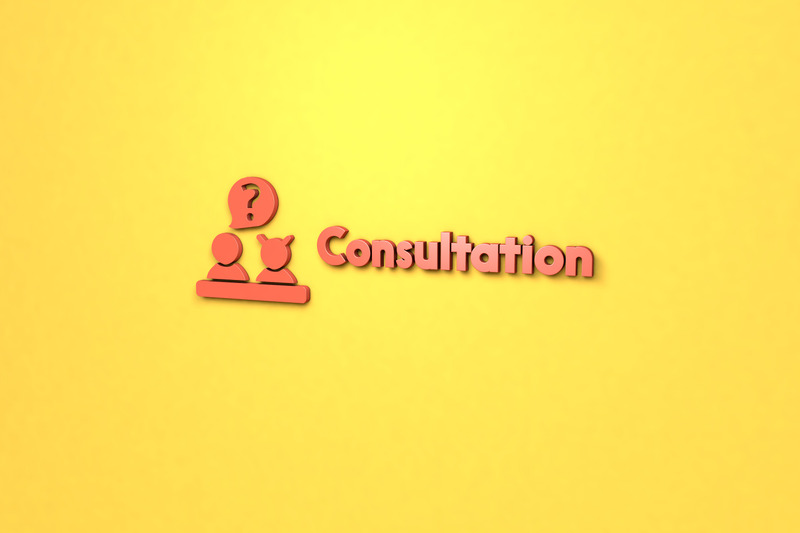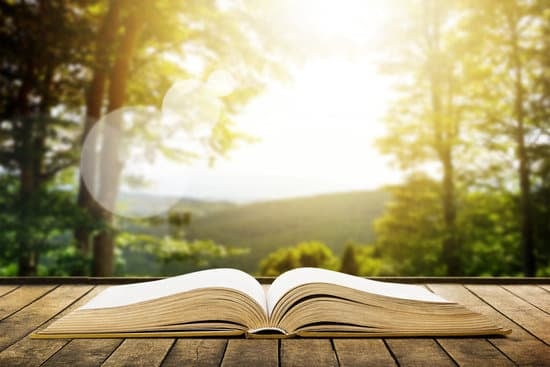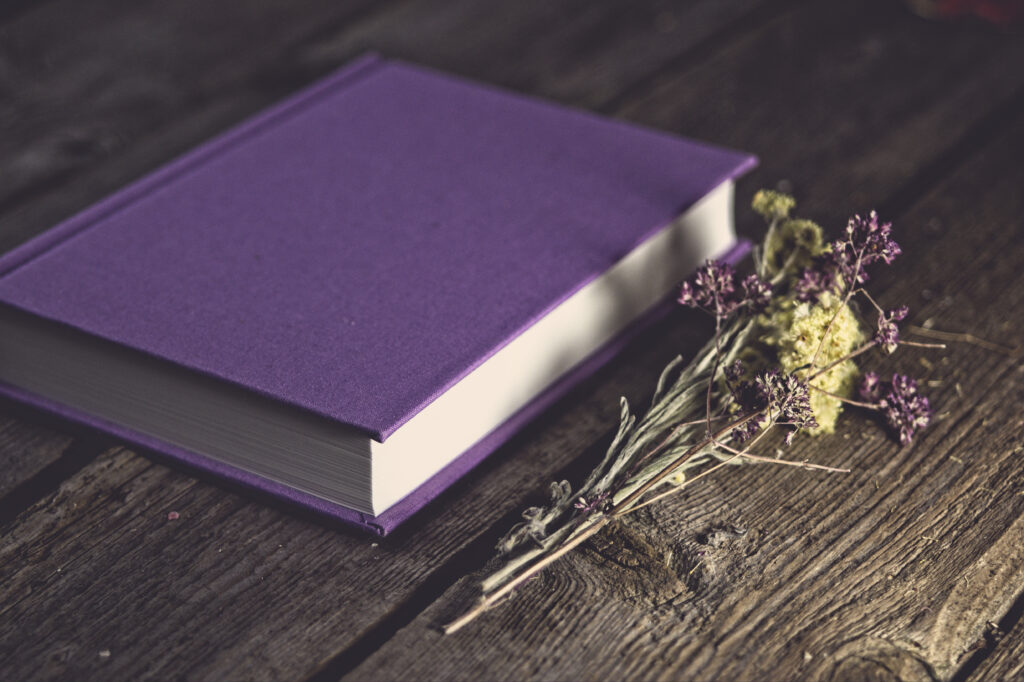ブログ
-

いただいた『無料相談』のご感想⑥【Sさまより】
少し前にはなりますがありがたいことに先日 わたしのLINE公式アカウントより無料相談のお申し込みをいただきました。 このところの記事でお伝えしているように今後、無料相談は各月ごとの相談回数を限らせていただく予定です。 詳しいことはnoteやインスタ... -

お客様の声🍀
先生の優しい声と口調に安心して相談することができました。「何でも吐き出してください」の言葉に、心の奥底に抑え込んでいた辛い過去の話も、水澤先生なら話しても大丈夫と思えて、涙ながらに吐露してしまいました 。教員として長年の豊富な経験と知識を... -

New✨ 個別サポートのご感想:Aさまより①
すみません🙇💦電子書籍出版📖に関する記事が続き本業の記事がしばらく途絶えていました🙏 というのも実はこのところ記事にしていた電子書籍出版に限らず 新たな波がつぎつぎと押し寄せてきて本当に、息をつく隙もなかったからです💦 そんな中、新たな試み... -

【内容紹介】電子書籍初出版📖✨タイトル*「GRIT(グリット)やり抜く力」の3つの鍵*
執筆はもちろん電子書籍として売り出すためのアカウント作成や出版のための申請など 初心者のわたしにとっては高く険しい数々のハードルを乗り越えながらたどり着いた電子書籍初出版📖✨ 本日は書籍の内容を紹介させていただきます。 Amazon本の紹介ページ... -

「良い面談」と「悪い面談」🤔?今もわたしの中に息づいていることとは!?
先日久しぶりにお申し込みいただいた個人相談からふと思い起こしたことがありました。 20年ほど前栃木県の総合教育センターに内地留学させていただいていた時に 保護者面談についての教員研究をする機会を得たときのことです。当時、センターでの研修に... -

いただいた『無料相談』のご感想⑤【Tさまより】
実はこのところ本業とも言える相談のお仕事からはやや遠ざかっていました。 というのも福祉施設での児童発達管理責任者(以後「児発管」)としての仕事が自分のキャパシティぎりぎりだったたからです。 ありがたいことにこのぎりぎりの期間まるで誰かに守... -

本の出版について☆現在地☆その③
本の原稿を書き上げて(たつもりで?)自分の中に思うところがあって いったん立ち止まって考えた時点での記事がこちら ⇓ https://note.com/embed/notes/n18c544d5e02e 一部センシティブな内容を含むので有料とさせていだたいています。 そこからあるきっ... -

覚悟とは??子どもの不登校に直面しても仕事を諦めなかった理由とは🤔?
こちらの記事 ⇓ https://note.com/embed/notes/n7e49969935d6 この記事から続く第1子が不登校というピンチに陥っても仕事を辞めなかったわけ…。 今回はこのことについて振り返ってみたいと思います。 若いころから子ども好きでした。(そう思い込んでい... -

年金??今後について今わたしが思うこと🤔💰
物価の高騰や社会保険料負担増などあまりにも重くのしかかる現実に 多くの国民が前回の選挙に多くの期待と関心を寄せたことがさまざまな情報から見て取れました。 確かにここのところの米だけに限らない食料品の高騰や じわじわと押し寄せてくるまた、われ... -

覚悟とは??振り返って今思うこと🤔
先日とあるご相談をいただきました。お子さまの行き渋り、不登校についてです。 そのことを振り返ってみて思い出したことがありました。 わが娘が不登校になったときのことです。 娘の愛着の問題についてはわが子たちが当時通っていた ピアノ教室の先生か...